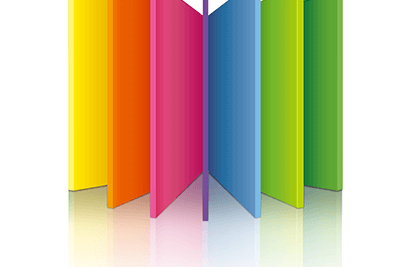放課後等デイサービスの将来性は?今後取り組むべきこととは

1990年代から2010年代にかけて、障害を持つ小中学生の数は増え続けているという調査結果があります。これらの子どもたちは数が増えたというよりも、今まで周囲の無理解などから見落とされていた例が改められたケースが多いのです。身体障害や発達障害をもつ子どもたちは、精神的肉体的に多くのニーズを抱えています。そこで、こうした子どもたちの受け皿となるために、学校が終わった後に学業や生活訓練を行う場所である放課後等デイサービスの存在が重要になってきているのです。
障がいを抱える子どもが増加傾向にある
全国の公立小学校、中学校に対する調査によると、1990年代から2010年代にかけての20年の間に、障害があると診断されて通級指導を受けるようになった児童生徒は、調査開始以前の約7倍にまで増えています。その総数は全国で9万人にのぼり、診断結果も四肢麻痺や知的障害、自閉症、ADHDや、高機能自閉症、アスペルガー症候群など多岐に渡ります。知的障害、身体障害は比較的早い時期から診断が下ります。しかし、自閉症などの発達障害は「親の育て方によるもの」という偏った見方が強く、多くの子どもたちが見過ごされていたのです。特に90年代までは親の責任を重視する傾向が強く、適切な指導を受けられなかった過去があります。
そのため、2000年代にかけて研究が進むと、発達障害は育て方ではなく先天的なものであることが明らかになり、障害児の数が急激に増える結果となったのです。それに伴って医師による診断基準も少しずつ改定されていきつつあります。そして、このような診断を受けた子どもたちは、特別支援学級においてその子にあった指導を受ける必要があります。それが進展して広まりつつあるのが、放課後等デイサービスなのです。
放課後等デイサービスは、以前は児童デイサービスとも呼ばれていました。その当時は児童が家庭に保護されるまでの時間、介助者が生活援助や学習指導を行う場所でしたが、現状では生活訓練や食事介助まで業態が広がってきています。
放課後等デイサービスにはどんなニーズがあるの?
放課後等デイサービスは、経営を行う事業所によって形態はさまざまです。塾のように学習指導を行ったり、ADLの改善のために自主自立を重んじた生活を送らせたり、中には給食サービスを行ったりする場所もあります。何故多様な事業形態が発展しているのかというと、障害とは1人1人が違うものを持っており、子ども1人1人に対する保護者のニーズも多種多様だからです。ある家庭ではコミュニケーション能力を訓練してほしい、またある家庭では集中力を身につけさせてほしい、あるいは自分で服の着脱ができるようになってほしいなど実にさまざまです。
そのため、放課後等デイサービスの将来性を失わないためにも、障害児を抱える保護者のニーズにこたえられる専門職の確保が欠かせません。児童福祉士、保育士をはじめ、介護ヘルパーや介護福祉士、言語聴覚士などの資格を持った職員を勤務させることが必要になります。現在専門職資格を持った求人は増えつつあり、それに伴って資格を取ることを希望する学生や主婦なども増えています。この機を逃さずに、所定のカリキュラムを修めた専業者をスタッフとして雇用することが、事業所の将来的な安定経営を行う上で欠かせない要素となっているのです。
放課後等デイサービスの今後取り組むべきこと
発達障害を持つ多くの子どもたちは、同世代の子どもたちとコミュニケーションをとることに非常な困難を抱えています。また視覚障害や四肢麻痺などで車椅子生活をしている児童生徒も、同級生たちと「同じように過ごせない」という不安な状況下で日々を過ごしています。放課後等デイサービスに求められていることとして、このような心に不安を抱えてしまった障害児たちと学校、友達、地域の架け橋となり、その中で安心して過ごせるようにフォローしていくことがあげられます。学校にいる間障害を持つ子どもたちは非常に緊張した時間を過ごします。そこは、正解、不正解という基準でのみ自分を測られることが多く、自身の持っている能力に応じて「できないこと」、不可能性を如実に思い知らされる場所であるからです。
こうした不安を解消することが、放課後等デイサービスを営む事業所の将来性につながります。学校や地域に居場所を持てない子どもたちや保護者たちの受け皿となることで、安定した利用者確保が可能になります。自分が責任者を務める事業所が利用者に選ばれ続けるためには、施設のブランディング化が重要なテーマです。ブランディングとは、他の施設にはない特色を持っていること。まず利用者である子どもと保護者から聞き取りをしっかりと行い、持っているニーズを踏まえてどのような指導方針を打ち立てていくか、適切な指導計画を策定していくことが経営者の責務なのです。
放課後等デイサービスはまだまだ新しい事業です。そのため、制度の改定も少しずつですが進められています。報酬単価も伸びてきてスタッフを雇用しやすくなっていくのもメリットです。子どもたちを守る新しい施設として、特色を出していくこと。それが長く経営を続けていくために事業者が努力し続けなくてはならないポイントとなります。
リコーリースの介護報酬・障がい福祉ファクタリングは、“負債”扱いにならずに“早期”資金調達ができる介護事業、障がい・福祉事業者向けの金融サービスです。最短5営業日で資金化も可能。サービスの詳細は下記バナーをクリックください。
けあコンシェルでは会員登録いただきますと『実践CaseStudy』や『介護Report』などの介護業界の旬な情報をご覧いただけます。
けあコンシェル会員登録をされた方は、必ず弊社サービスをお受けいただくということではございませんので、お気軽にご登録ください。
厚生労働省は介護職員等の賃上げ対応として2026年6月に臨時の介護報酬改定を行う方針を12月12日の社会保障審議会・介護給付費分科会に示した。その中身では、▽現行の「介護職員等処遇改善加算I、II」に生産性向上や...
厚生労働省は、15日に開催された社会保障審議会・福祉部会に、地域共生社会の更なる展開などに関する報告書案を提示した(資料P1参照)。委員からは賛成の意見が示され、報告書案は部会長一任で了承された。同部会で...
社会保障審議会・介護保険部会が15日に開催され、取りまとめに向けた議論を行った。厚生労働省は、「介護保険制度の見直しに関する意見」(案)および持続可能性の確保に関する各論点について、これまでの議論を整理...
社会保障審議会・介護保険部会は1日、ケアマネジメントへの幅広い利用者に利用者負担を求める方向性について議論を行った。現行で10割給付のケアマネジメントに利用者負担を導入する提案には、委員から導入を進める...
厚生労働省は介護保険の能力に応じた負担で「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準を整理し、1日に開催された社会保障審議会・介護保険部会で介護保険における利用者の2割負担の対象範囲拡大に関する具体案を...
>>その他サービスを見る
早期資金化!介護報酬ファクタリングサービスで解決!現行の介護保険制度では、国民健康保険団体連合会(国保連)から介護報酬を受け取るまでに約2ヶ月かかり、その間に発生する人件費など資金が必要になります。リコーリースの「介護報酬ファクタリングサービス」を利用すれば、通常より1.5ヶ月も早く資金化することができます。
ご利用者様の預金口座から利用料金を口座振替いたします。弊社の口座振替ネットワークを利用して、電気料金などの公共料金と同じように、ご利用者様の預金口座から利用料を口座振替するシステムです。振替日は4日、20日、27日をご用意しております。
車両リースは、資金の効率的な活用を実現し、メンテナンスなど煩雑な管理業務もアウトソーシングできるため多くの企業に採用されています。一般的に車両リースを大別すると、ファイナンスリースとメンテナンスリースに分類することが出来ます。
商圏分析サービスとは、これからデイサービスの開業をお考えの方、既にデイサービスを開業しており増店をお考えの方へ出店したい地域の情報を提供させていただくサービスです。簡易版では、出店したい地域の商圏内における3種類のレポートを「けあコンシェル」会員様限定で無料にて提供いたします。
利厚生の充実は、優秀な人材確保の切り札です。アウトソーシングサービスを活用することで、豊富で充実したメニューを従業員やそのご家族の皆様へ提供でき、満足度を向上することができます。

 けあコンシェルとは
けあコンシェルとは