
【コロナ対策】介護職員ができるリモートケアにはどんなものがある?
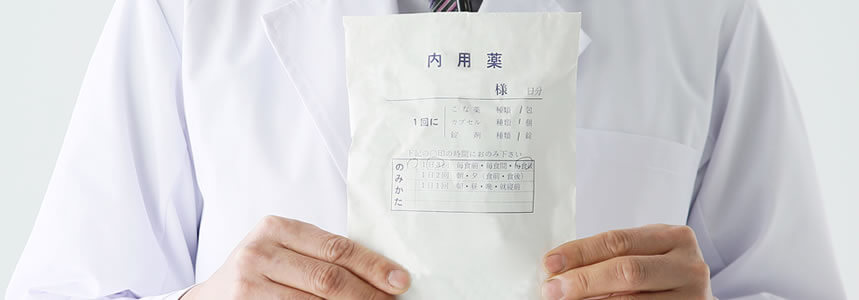
【コロナ対策】介護職員ができるリモートケアにはどんなものがある?
コロナ禍で自粛が続くなか、介護業界にもリモートによるコミュニケーションの活用が求められています。この記事では、利用者との接触が多く、新型コロナウイルスへの感染リスクが高い介護の現場で使えるリモートケアについて紹介します。リモートケアでコミュニケーションを取るときのポイントや、職員間の連携の取り方も説明しますので、参考にしてください。
コロナ対策, リモートケア
1.介護現場は新型コロナウイルスの感染リスクが高い
介護サービスでは、支援や介護をする際に担当者が高齢者に触れる場面が多くあります。そのため、介護の現場では、利用者や介護職員が密接にかかわることは避けられません。それにより、介護事業所は新型コロナウイルスへの感染リスクが高いと考えられています。高齢者への感染は重症化するなどのリスクが高い上に、クラスターも発生しやすいとされているのです。コロナ対策として、国は介護事業所に対してリモートを活用するケアを推奨しています。新型コロナウイルスの流行中は、介護現場でも、できるだけ工夫して利用者との接触を少なくする必要があるのです。
2.高齢者に対するリモートケア
介護事業所では、高齢者が人との接触をできるだけ減らすための対策として、リモートケアが求められています。ここでは、オンラインでできるモニタリングやシニアヨガについて紹介しますので、ぜひ取り入れていきましょう。
2-1.オンラインでのモニタリング
従来の訪問による見守りは、利用者が新型コロナウイルスへの感染リスクに配慮し、利用を控える動きが高まってきました。そのため、人との接触なしに見守りができるオンラインでのモニタリングが注目されています。見守りセンサーやロボットなどの情報通信技術(ICT)は、高齢者の見守りやコミュニケーションに活用できるものです。電話だけでは見逃しがちな、利用者の精神的な変化も察知できる可能性が高いツールとして評価されています。ほかにも、施設での入居者への面会が制限されているため、オンラインで家族と入居者が面会するなどの工夫も行われています。面会ができない事態が続くよりも、少なくともリモートケアでコミュニケーションがとれれば、高齢者や家族にとって安心感が得られるでしょう。
2-2.オンラインシニアヨガ
コロナ禍での自粛で通所を控える方が増え、自宅にいることが多くなれば高齢者の運動不足は避けられません。ヨガは、高齢者でも無理なくできる動作をすることにより、認知症予防や筋力・柔軟性を高めるなどの効果が期待されているものです。日常のケアのなかにヨガを取り入れている事業所や病院なども増えてきました。椅子に座って様々な所定の動作をするなど、高齢者でも簡単にできるのが「シニアヨガ」です。コロナ禍においては、介護者がリモートで、個々の状態に合わせてヨガのポーズを指導すれば、通所で行うのと同じような効果も期待できるでしょう。自宅にいても気軽にできるシニアヨガを楽しみ、コロナ禍での自粛のなかでも健康的な生活を送ってほしいところです。
3.介護職員による職員間でのリモートコミュニケーション
介護職員の業務には、利用者への直接的なケア以外ならリモートでできるものが多くあります。例えば、介護職員が従来のような会議を行うと「3密」になることは避けられません。できるだけ接触を避けながらコミュニケーションを円滑にするためには、チャットツールやWeb会議などを活用していく必要があります。スマートフォンやタブレットなどの端末があれば、どこにいても簡単に記録や連絡などの作業が可能です。対面しなくてもコミュニケーションが取れる方法を積極的に取り入れていけば、新型コロナウイルスの感染リスクを減らすことにつながります。コロナにより分断される人とのつながりは、リモートコミュニケーションの活用で復活させていきましょう。
4.介護現場の感染防止策
利用者との接触が避けられない介護の現場では、コロナ対策を徹底しなければなりません。厚生労働省が示している感染防止策には、マスクの着用や手洗い、アルコール消毒、毎日の検温などがあります。これは、介護事業所の職員だけでなく、利用者やその家族、業者、ボランティアなど事業所に出入りする人、全員が行う必要があるものです。施設に入所している場合は、緊急時などのやむを得ないときに限り面会できるといった制限も求められています。利用者に発熱などの症状があれば別室に隔離し、可能であれば、担当者を限定するなどの措置も推奨されています。特に、基礎疾患のある利用者に発熱などの症状があれば、帰国者・接触者相談センターなどの窓口に相談し、感染が拡大しないよう配慮しなければなりません。
5.もしもクラスターが発生してしまったら
同じ空間で過ごすことの多い介護事業所では、新型コロナウイルスの感染者が出てしまった場合、クラスターになりやすいと考えられます。日ごろからクラスターが発生した場合を想定し、介護職員が不足しないよう人材確保をしておく必要があるでしょう。しかし、余裕のある人員配置をしている事業所ばかりではないのが現状です。クラスターが発生した場合に備えて、国はほかの社会福祉施設などから応援職員を派遣する支援策を提示しているので、万一の場合は利用できるでしょう。また、高齢者は、ほかの年代よりも重症化しやすいといわれているため、新型コロナウイルスへの感染が判明した時点で入院の措置をとるのが原則です。ただし、実際には地域での発生状況などにも配慮する必要があるため、専門家に相談しながら助言に従って対応するようになります。
6.現場にかかっている負担!事業所の資金繰りを楽にするために
コロナ対策として、介護の現場では人との接触を減らすための工夫である「リモートケア」などの取り組みが進められています。基本的な感染症対策を徹底しながら、万が一のクラスター発生にも備えて人員確保をしておきたいところです。人件費などの増大にともなう負担に悩むときには、リコーリースの介護報酬ファクタリングサービスの利用をおすすめします。初期審査料や更新料は無料、連帯保証人なども不要なので簡単に利用できます。介護保険給付費を早期回収するためのサービを活用し、負担を減らしていきましょう。
リコーリースの介護報酬・障がい福祉ファクタリングは、“負債”扱いにならずに“早期”資金調達ができる介護事業、障がい・福祉事業者向けの金融サービスです。最短5営業日で資金化も可能。サービスの詳細は下記バナーをクリックください。
けあコンシェルでは会員登録いただきますと『実践CaseStudy』や『介護Report』などの介護業界の旬な情報をご覧いただけます。
けあコンシェル会員登録をされた方は、必ず弊社サービスをお受けいただくということではございませんので、お気軽にご登録ください。
社会保障審議会・介護給付費分科会が12月26日に開催され、厚生労働省は2027年度以降の地域区分について、26年末頃に市町村に提示すると報告した(資料P2参照)。 介護報酬は公務員の地域手当に準拠し、人件費の...
厚生労働省は12月26日、予算大臣折衝を踏まえた2026年度に行う臨時的な介護報酬改定の概要を社会保障審議会・介護給付費分科会に報告した。臨時改定の改定率は+2.03%。このうち介護分野職員の処遇改善が+1.95%で...
厚生労働省は17日、介護分野における「医療・介護等支援パッケージ」および重点支援地方交付金について、都道府県や市区町村に対し、早期の予算化と速やかな執行を求める事務連絡を出した(資料P1~P3参照)。今回の...
上野賢一郎厚生労働相は24日、片山さつき財務相との折衝後の記者会見で、2026年度に実施する臨時介護報酬改定の改定率が+2.03%の引き上げとなったことを発表した。 上野厚労相は臨時の介護報酬改定、障害福祉...
Q. 2025年度補正予算で手当される介護事業所・施設のサービス継続支援事業の内容を教えてください。2025年度の補正予算では介護職員等の処遇改善の支援に加えて、経営難に苦しむ介護事業所・施設が介護サービスの提...
>>その他サービスを見る
早期資金化!介護報酬ファクタリングサービスで解決!現行の介護保険制度では、国民健康保険団体連合会(国保連)から介護報酬を受け取るまでに約2ヶ月かかり、その間に発生する人件費など資金が必要になります。リコーリースの「介護報酬ファクタリングサービス」を利用すれば、通常より1.5ヶ月も早く資金化することができます。
ご利用者様の預金口座から利用料金を口座振替いたします。弊社の口座振替ネットワークを利用して、電気料金などの公共料金と同じように、ご利用者様の預金口座から利用料を口座振替するシステムです。振替日は4日、20日、27日をご用意しております。
車両リースは、資金の効率的な活用を実現し、メンテナンスなど煩雑な管理業務もアウトソーシングできるため多くの企業に採用されています。一般的に車両リースを大別すると、ファイナンスリースとメンテナンスリースに分類することが出来ます。
商圏分析サービスとは、これからデイサービスの開業をお考えの方、既にデイサービスを開業しており増店をお考えの方へ出店したい地域の情報を提供させていただくサービスです。簡易版では、出店したい地域の商圏内における3種類のレポートを「けあコンシェル」会員様限定で無料にて提供いたします。
利厚生の充実は、優秀な人材確保の切り札です。アウトソーシングサービスを活用することで、豊富で充実したメニューを従業員やそのご家族の皆様へ提供でき、満足度を向上することができます。

 けあコンシェルとは
けあコンシェルとは








