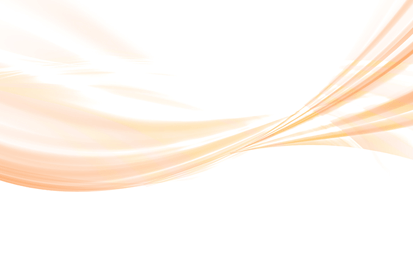厚生労働省も認める保険外サービスの活用法とは?

平成30年の介護報酬、診療報酬のW改定に向けて日々議論が進められています。介護業界で目下の関心事といえば、介護保険サービスの範囲がどの程度縮小するのか、またそれに伴い保険外サービスがどこまで広がるのかではないでしょうか。厚生労働省も保険外サービスの活用には積極的であり、今後ますます利用されるようになるのが必然の流れとなっています。ここでは保険外サービスの有効な利用法について考えていきましょう。
うまく活用するには厚生労働省のガイドブックを参考にしよう
厚生労働省によると、現在の介護保険で提供されているサービスは全25種類53サービスとされています。これが多いと感じるか少ないと感じるかは人によって異なるでしょう。しかし保険外サービスがこれを遥かに上回る種類で展開されることは、まず間違いがありません。家事代行サービスや保険外で通常のヘルパー業務プラスアルファを行うホームヘルプサービスなど、介護保険に類似もしくは上乗せされる形のサービスだけでなく、配食サービスやトラベルヘルパーなどの、介護保険とは全く異なる分野を開拓しているサービスもあります。
百花繚乱の様相を呈している保険外サービスですが、それだけ種類が増えてしまうと利用者にとってわかりにくくなってしまう可能性も否めません。とりわけサービスの利用者は高齢者ですから、十分な判断力を有していない人を相手に契約を結んだり、十分な説明のないまま付加サービスを行ったりといった、保険外サービスを悪用するケースも想定されます。
このようなケースに対する危惧、そして事業所が高齢者にとって有用な保険外サービスを提供することを求めて、厚生労働省は平成28年3月にガイドブックを策定しました。ここには保険外サービスの先行事例がいくつも収められているだけでなく、その理念や意義といった面にも触れていますから、これから保険外サービスを展開しようと考えている事業所にとって、非常に有用な内容となっています。
参考=厚生労働省 地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集(保険外サービス活用ガイドブック)(PDFファイル 21MB)
保険外サービスの魅力はどこにあるか
厚生労働省が発表しているガイドブックを読めば、保険外サービスがいかに多様なものであるか一目瞭然です。介護保険の枠内では提供できるサービスも、事業収入の上限も定められているようなものでしたが、保険外サービスではその制限がなく、利用者のニーズに合わせたサービスを柔軟な値段設定で提供することが可能となります。介護保険事業だけでは苦しい状況にある事業所にとって、まさに渡りに船の状況です。
介護従事者にとっても保険外サービスは魅力的です。値段設定が自由であることはつまり、頑張れば頑張るだけ評価がされやすい土壌作りがなされるということになります。ホームヘルパーの指名制度をとっている事業所であれば、指名が多ければ多いほど収入が増える仕組みをとっています。ケアの質を高めればそれだけ金銭的な見返りが得られるのは、介護士としても大きなやりがいではないでしょうか。
最後に保険外サービスの利用者にとってもメリットをみてみましょう。保険外サービスの良いところは、なんといっても「痒いところに手が届く」ことです。介護保険サービスではできなかった「あと少し」の部分を担ってくれるサービスに対し、上乗せした金額を支払っても良いという人は少なくないでしょう。基本的な部分は介護保険でまかない、あと少しの部分を保険外サービスでしてもらえば、金銭的にも大きな負担にはなりません。
質の高い介護を目指して保険外サービスを活用する
事業所にとっても介護士にとっても、そして利用者にとってもメリットのある保険外サービスですが、デメリットがまったくないのかといえば、そうではありません。付加サービスを提供することになればその分だけ上乗せした金額を支払う必要があるでしょうし、それを払えない人にとっては絵に描いた餅となるでしょう。貧富の差によって介護という社会福祉サービスに差が出てもよいのか、という点に関しては今後まだまだ議論が必要です。とはいえ、現行の介護保険制度が財政的に続けられないのは火を見るよりも明らかであり、どんな形になるにせよ保険外サービスの活用は不可欠な状況です。この状況下において、保険外サービスをどのように使えばよいのでしょうか。
鍵となるのはケアマネージャーの存在です。保険外サービスは有効に使えば便利なものですが、使いすぎると金銭的な負担が増大するだけでなく、その人のできることまで奪ってしまい本人の活動量の低下を招く危険性があります。判断力が低下している高齢者にとって、どのサービスを使えば自分にとって一番良いのか、その場で決定することは困難です。そのようなときにケアマネージャーがあいだに入ってサービスの選り分けを行うことで、本人の生活の質(QOL)を高める保険外サービスの選択が可能となるでしょう。またサービスだけでなく事業所の選別も、ケアマネージャーに課せられた重要な役割となりそうです。
保険外サービスは上手に利用すれば、QOLを高める有用なものとなります。有効利用のためには介護保険の基本理念、自立支援を忘れないようにしたいものです。
リコーリースの介護報酬・障がい福祉ファクタリングは、“負債”扱いにならずに“早期”資金調達ができる介護事業、障がい・福祉事業者向けの金融サービスです。最短5営業日で資金化も可能。サービスの詳細は下記バナーをクリックください。
けあコンシェルでは会員登録いただきますと『実践CaseStudy』や『介護Report』などの介護業界の旬な情報をご覧いただけます。
けあコンシェル会員登録をされた方は、必ず弊社サービスをお受けいただくということではございませんので、お気軽にご登録ください。
厚生労働省は2024年度の介護報酬改定に関するQ&A(Vol.15)の事務連絡で、訪問リハビリテーションの診療未実施減算の「適切な研修の修了等」について、日本医師会の「かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を...
Q.2024年度改定後、介護職員の賃上げは進んでいるのでしょうか?2024年度介護報酬改定では3つの処遇改善関連加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化され、加算率も引き上げられましたが、効果は現れているので...
東京商工リサーチは7日、訪問介護事業者の2025年上半期(1-6月)の倒産件数が、2年連続で過去最多を更新したと発表した。 倒産件数は45件(負債額1,000万円以上)で、前年同期比12.5%の増。これまでは小規模...
Q.介護休業の対象が拡大されたそうですが、どのような改正があったのか教えてください介護休業の適用範囲が広がり、障害のある子も対象に含まれるようになったそうですが、具体的な変更内容について詳しく教えてく...
厚生労働省が行った調査によると、2024年6月30日時点で未届けの有料老人ホームの割合は3.3%で、前年度から0.2ポイント低下した(参照)。厚労省では、届け出義務があるにもかかわらず未届けで運営している有料老人ホ...
>>その他サービスを見る
早期資金化!介護報酬ファクタリングサービスで解決!現行の介護保険制度では、国民健康保険団体連合会(国保連)から介護報酬を受け取るまでに約2ヶ月かかり、その間に発生する人件費など資金が必要になります。リコーリースの「介護報酬ファクタリングサービス」を利用すれば、通常より1.5ヶ月も早く資金化することができます。
ご利用者様の預金口座から利用料金を口座振替いたします。弊社の口座振替ネットワークを利用して、電気料金などの公共料金と同じように、ご利用者様の預金口座から利用料を口座振替するシステムです。振替日は4日、20日、27日をご用意しております。
車両リースは、資金の効率的な活用を実現し、メンテナンスなど煩雑な管理業務もアウトソーシングできるため多くの企業に採用されています。一般的に車両リースを大別すると、ファイナンスリースとメンテナンスリースに分類することが出来ます。
商圏分析サービスとは、これからデイサービスの開業をお考えの方、既にデイサービスを開業しており増店をお考えの方へ出店したい地域の情報を提供させていただくサービスです。簡易版では、出店したい地域の商圏内における3種類のレポートを「けあコンシェル」会員様限定で無料にて提供いたします。
利厚生の充実は、優秀な人材確保の切り札です。アウトソーシングサービスを活用することで、豊富で充実したメニューを従業員やそのご家族の皆様へ提供でき、満足度を向上することができます。

 けあコンシェルとは
けあコンシェルとは